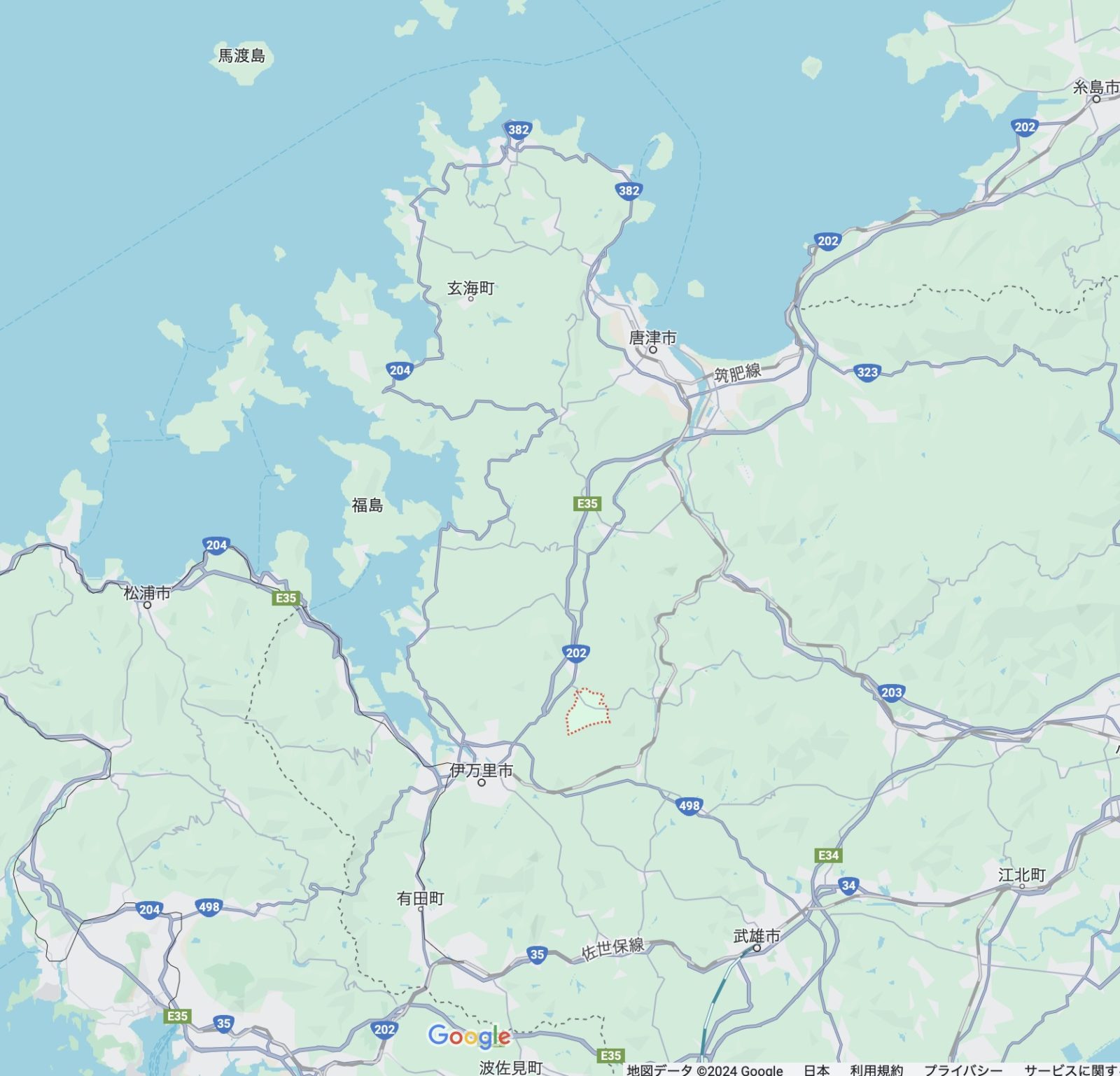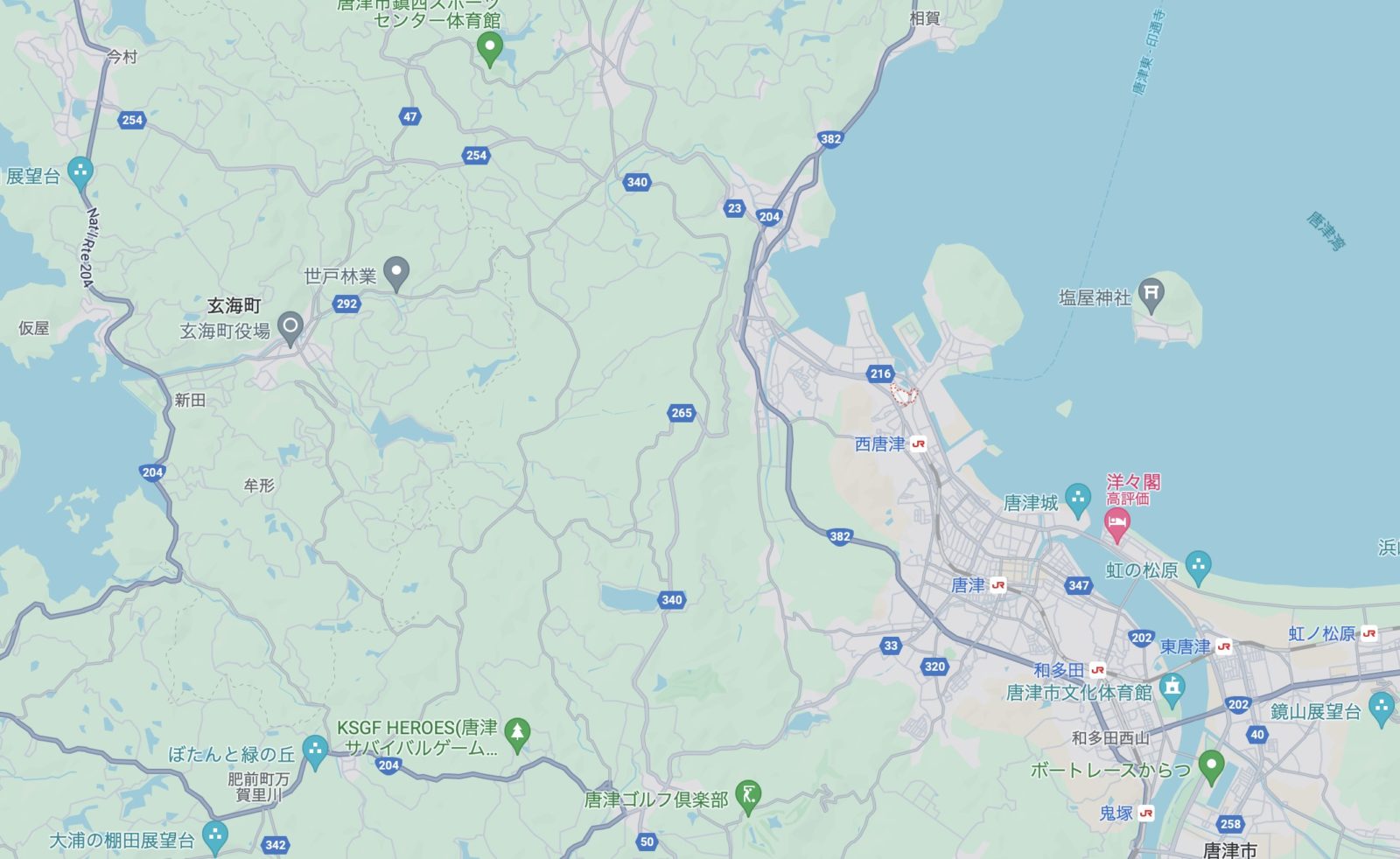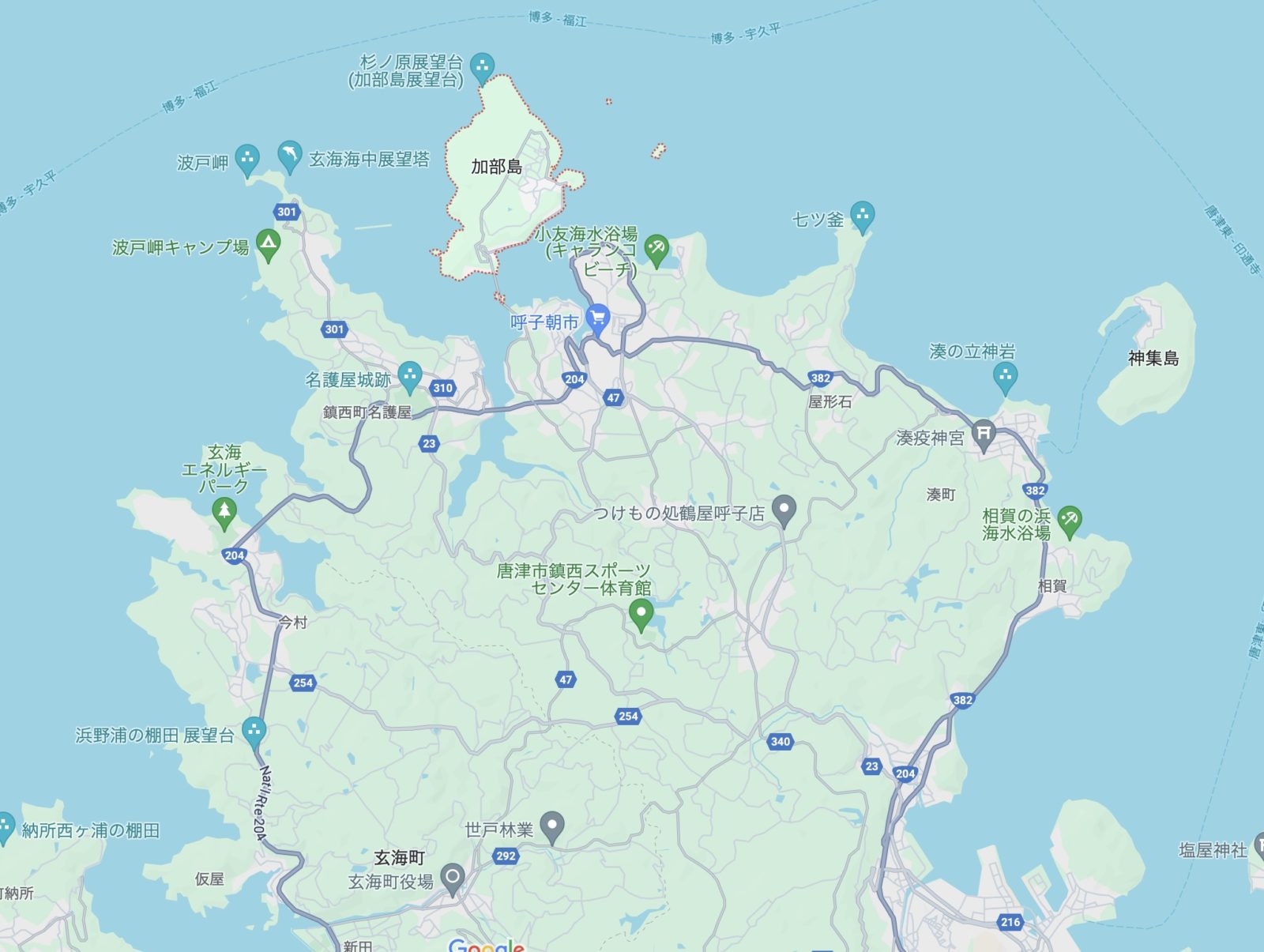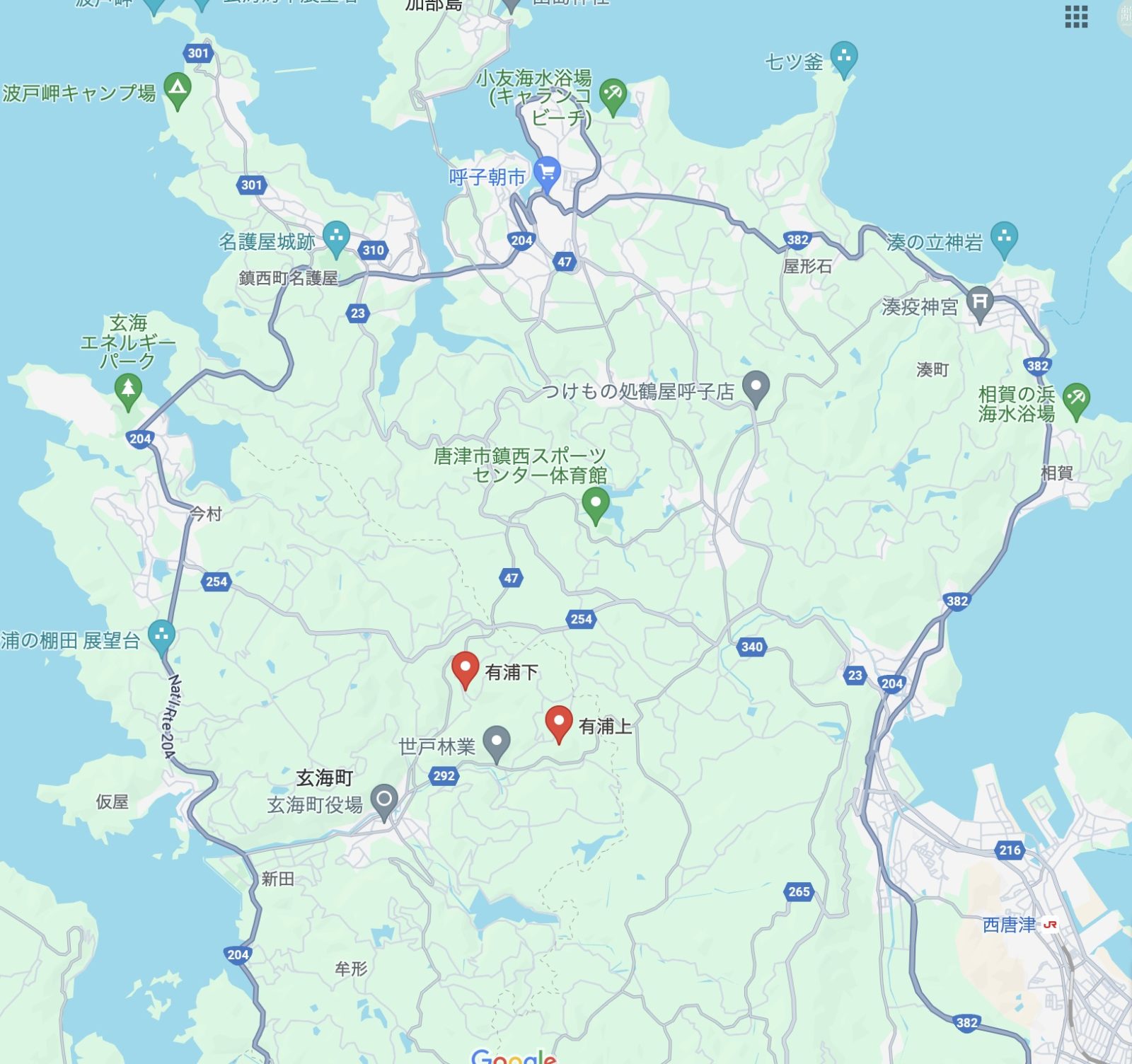信楽で作陶されている谷穹さんの工房の隣には、お祖父様が蒐集された古信楽の壺がたくさん収蔵された展示室があります。骨董商を営んでいたとはいえ、個人が集めたとは思えないその量と質は驚くべきもので、公のもの含め、古信楽のコレクションとしては国内でも群を抜いています。そのような優れたコレクションに囲まれて育ったからか、谷さんの古信楽に対する情熱と考察は比類なきものです。
近現代の信楽焼と古信楽は何かが違う。では何が、どのように違うのか。谷穹さんはその違和感に蓋をせず、透徹した眼で観察し、そして実際に窯焚きしながら検証していきます。谷穹さんの作品にあって、なんとなくのフォルム、偶然の窯変というものは、存在しません。谷さんは自身の研究によって、窯変も計算し狙って出せることを体験しているからです。古信楽に関する研究がほとんどされていない状況で、谷穹は独り、古信楽を「正しく」現代にアップデートする作業を行っているのです。
また谷さんといえば壺。
食器や茶道具は、それを使ってはじめて立体化する=活かされるという部分があります。
つまり何かを入れるものとしての「器」は、何かを入れてこそ、使ってこそのもの。
対して、壺というのは、もちろん貯蔵などの実用性が付与されるという側面はありながらも、それはどちらかといえば二次的で、(この反転は歴史的にいつ頃から発生したのか、あるいはもともとそのような感覚を与えるものとしてあり続けたのか)その意味で、壺は「器」であって器ではないと思います。
壺をつくる作家が、壺に魅せられているのも、まずもって壺の持つこのような自立/自律性に孤高の美を見いだすからなのでしょう。
要するに壺は、使うものとの親密な関係性を結ぶことを目的とせず、生活の中にありながら、生活における他者として存在し、わたしたちを眼差している。
壺とわれわれの間には冷厳たる隔たりがあり、それゆえにこそ美しいのだともいえます。だから壺は人が作りだすもののなかで、最も「自然」に近いのではないでしょうか。
壺が魔力や霊力を持つもみなされるのも、他者性をはらむ自然そのものとして、自立しながらわたしたちのそばに現れるからだと思います。
それゆえ、壺は危うくもある。壺は永遠にその本質を表さない謎として存在し続け、壺を語る言葉も、その表面を撫でるだけで、決して本質を掴まえることができない。
壺が「分かる」というのは、もしかしたら禅が「分かる」というのに似ているのかもしれません。不立文字の壺。答えではなく、問いとして表れるかたまり。Q。
谷穹さんの作品は、無益と知りつつも、その謎を解き明かしたくなるような魅力を持っています。
もちろん、言葉は要らず、ただ傍らに置いておくだけで十分なのですが。
1977年 滋賀県信楽出身
2000年 成安造形大学 立体造形クラス卒業
2007年 双胴式穴窯 築窯
2012年 穴窯 築窯